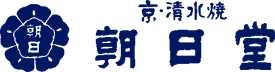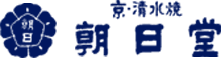京都の代表的な伝統工芸品の一つ、京焼・清水焼

日本中から選りすぐりの材料と職人が集う街で栄えた焼き物
「京焼」は、茶の湯の流行を背景に、江戸時代初期頃から東山山麓地域を中心に広がった焼き物のこと。対して「清水焼」は、清水寺の参道である五条坂で作られていた焼き物でした。現在は、京都で焼かれる焼き物全般を「京焼・清水焼」と呼んでいます。


形も絵付けも様々。すべての技法が融合
「京焼・清水焼」には特定の様式・技法があるわけではなく、全ての技法が融合されています。その背景には、都のあった京都が、日本中から選りすぐりの材料と職人が集う街であったという恵まれた環境と、その文化を後援する寺社仏閣、皇族、貴族などの存在があったことがあげられます。